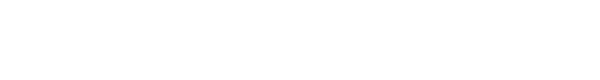皆さんこんにちは。弁護士髙砂美貴子です。
2020年(令和2年)春から猛威を振るった新型コロナ感染症により窮境状態に陥った事業者も、特例融資や国税猶予制度でどうにか当面の資金繰りが回ったところが多かったようです。
しかし、国税の猶予期間中も公租公課は発生し続けますし、納税猶予も一時的なものですので、今後未払いの公租公課が支払えず倒産せざるを得ない会社も出てくるでしょう。
また、いわゆる「ゾンビ企業」も多数存在しているといわれており、2021年度時点で約18万8000社と新型コロナウイルス禍前の19年度と比べると約3割増えました。帝国データバンクが26日公表した調査によると、ゾンビ企業は2年連続で増え、13年度(約20万社)以来の高水準となり、19~21年度の間に4.2万社増えた。コロナ禍に対応した実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」などで、過剰債務を抱える企業が増加したことが原因と思われます(「ゾンビ企業18.8万社に増加 21年度、ゼロゼロ融資で拍車」(日経2022年12月26日)(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB238LB0T21C22A2000000/)。
「ゾンビ企業」
1990年代前半にバブル経済が崩壊し、その後に日本経済が停滞した「失われた10年」を分析する際に専門家が使い始めた言葉とされる。数年にわたって債務の利払いすらままならず経営が破綻状態にあるのに、銀行や政府などの支援によって存続し続けているような企業を指す。バブル崩壊後の銀行は多額の不良債権を抱えており、早く処理しようとすれば銀行の財務内容が悪化して経営が揺るぎかねなかった。銀行は処理を先送りするために、再建の見込みがない企業に「追い貸し」をして延命した。ゾンビ企業が増えたことで経済の効率性が下がり、日本経済の成長を妨げたといわれる
※出典:「日経」2019年2月9日(https://www.nikkei.com/theme/?dw=22A00398)。
このような事業体であっても、事業を買い取りたいというスポンサーがみつかるケースもあります。競合他社が自社の販路拡大や技術的補完を目的として事業譲受を希望するほか、取引先や親族等の関係者が、破産の危機にある会社の事業を譲り受ける形で、当該事業を継続させ従業員やその家族の生活、商品サービスを守りたいというニーズがあることも考えられます。そのため、今後、破産局面において事業譲渡を検討すべき事案は増えてくるのではないかといわれています。
そこで、本稿では、破産局面における事業譲渡の活用について、その留意点や展望について概観したいと思います。
目次 非表示
この記事でわかること
- 早期に相談することの重要性
- 破産事案でも事業を残す余地はあるのか
早期に相談することの重要性
私が倒産法実務を学ぶ際、いつも参考にさせて戴いている書籍の中で、「『よい事業譲渡』は究極の財産保全である」という言葉がありました。
破産管財人として破産財団に属する資産を売却・換価するとき、「このまま事業を継続できればこの物件を立ち退く必要はないのに」、「この事業用資産をこの値段で処分するのはもったいないな」と感じることが多々あります。破産管財人として事業用資産を換価する場合、ほとんどの場合高値では売却できません。法定耐用年数が過ぎていればゼロ、事業を継続させない(廃業させる)のであればゼロです。
しかし、個々の事業用財産をバラ売りするよりも、有機的一体として機能している「事業」として売却すれば、より高額での換価が見込める可能性が出てきます。処分費用を考慮するとマイナスになってしまうような事業用資産であっても、事業が継続できれば逆にプラス評価される余地が出てくるわけです。
そのため、結果として破産を申し立てるしかない事案であっても、どうにかして事業を存続させられないかを検討する姿勢は重要だと思います。
なお、資金調達に失敗して開発費用を工面できず、やむなく破産を選択せざるを得ない状況に至ったスタートアップ企業からの相談を比較的多く受けるようになった、という話も耳にしました。スタートアップというとエクイティで資金調達しているイメージが多いと思いますが、実際は外部借入を併用しているところも多いようです。スタートアップで、しかも開発途上となりますと目ぼしい事業用資産がありませんから、中途の開発事業を第三者に事業譲渡して、譲受側で開発事業を引き継いでもらうというニーズもあります。このようなケースではなおさら、相談を受けた弁護士としては単に破産させるだけではなく、適正な手段によりできる限り事業を継続させられないか、適切な第三者に事業や資産を引き継げないかという点を検討することが重要になってくると思います。
もっとも、経営者(創業者)の中には、「この事業は一代限り」などと言って、頑なに事業継続を拒む方も一定数いらっしゃいます。「創業家が経営権を掌握できなくなるのであれば、この会社を存続させる意味はない」などと言って、「死なばもろとも」と言わんばかりに廃業前提の破産を選択しようとする方もいらっしゃいます。弁護士はあくまで代理人であり、相談者である経営者の意思を尊重することが最重要のミッションですので、このようなご相談者の場合どこまで説得するかは悩ましいところです。やはり「この事業を残したい」という経営者(創業者)の強い意志が不可欠ですので、経営者が廃業前提の破産にこだわるのであれば、代理人弁護士としてはいかんともし難いと言わざるを得ません。
しかし、経営者が誤った(というより、不十分な)理解のまま廃業前提の破産しかとりえないと思い込んでいるだけなのであれば、弁護士としてはそのような誤った判断を是正するよう努めなければなりません。
事業譲渡は、単純な資産換価よりも高額の回収を見込める可能性がありますし、破産手続との関係では、賃借物件の明渡費用や給与等の優先債権を圧縮することにつながりますので、メリットは大きいと思います。
一般的に、経営者は、取引先や従業員に迷惑をかけたくないと考える方が多いので、弁護士が事業譲渡のメリットを丁寧に説明すれば、本当に資金ショートして廃業前提の破産を申し立てざるを得ない状況に陥る前に、経営者が戦略的に決断するインセンティブになると思うのです。
そのためには、「弁護士に相談したら有無を言わさず破産させられる」などというネガティブなイメージを払拭するよう、弁護士側が努力しなければなりません。同時に、実際に相談を受けた弁護士も、破産局面でも事業譲渡により事業を存続させるという方法を選択肢のひとつとして提示していくべきだろうと思います(但し、ご相談者の財務状況や資金繰り等を総合考慮し、この手法が採れない場合、やむなく廃業前提の破産を申し立てることになろうかと思います)。
最後に
このように、最終的に破産を申し立てざるを得ないとしても、一定の条件がそろえば事業譲渡という選択肢を取りうる余地がある場合があります。もちろん、結果として事業が残せない事案(実際にはこちらのほうが多いかと思います)もありますが、そのような事案でも、できるだけ関係者への影響を小さくできるよう、いかにソフトランディングさせるかという視点を持ち続けることは重要だと思います。そのためにも、土壇場になって駆け込むのではなく、できる限り早く、いくつも選択肢が残されている段階で弁護士にご相談いただきたいと思います。